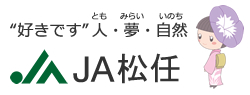
農業用語説明
| アルカリ性土壌 (あるかりせいどじょう) |
・ph が7 より大きくアルカリ性反応を起こす土壌。 ・土壌のアルカリ性程度は次のように示され、ph8以上の土壌では作物の生育は悪くなる。 |
| アントシアン | ・花、果実、葉、根の赤、青、紫、紫黒色などの色のもととなる色素。 ・細胞の液胞内に溶液として存在する。 |
| 暗好性種子 (あんこうせいしゅし) ⇔明発芽種子、好光性種子 |
・別名『嫌光性種子』。暗黒下で発芽が促進される種子。 ・トマト、ナス、ウリ類、ネギ属の数種、カボチャなどがこれにあたる。 |
| アンモニア態窒素 (あんもにあたいちっそ) |
・ある種のアミノ酸や尿素などの簡単な構造の有機態窒素も直接植物に吸収されて窒素の供給源となるが、『アンモニア態窒素』と『硝酸態窒素』が植物に吸収利用される主な形である。 |
| 移植(いしょく) | ・植物を今まで育ってきた場所から他の場所に植え替えること。 ・収穫までおくべき場所へ移植することを『定植』といい、定植までの間に苗床間で行なう移植を仮植という。 |
| EC(いーしー) | ・別名『電気伝導度』、溶液となっている塩類は電解質で電気をよく通すので、電気伝導度を測ることにより土壌中における養分含量の目安となる。 |
| 晩生(おくて、ばんせい) | ・作物など、暦の上で収穫期の遅いもの・収穫までの栽培期間が比較的長いもの。 |
| 親づる(おやづる) | ・ウリ類などの『つる』のうち、幼芽が直接伸びやもの。 ・親つるから一次的に分岐したつるが子づる。子づるから分岐したつるが孫つる。 |
| 花芽分化 (かがぶんか) |
・花芽形成の初期に、花の各部のもと(原基)ができること。 ・作物により温度、日照等さまざまな条件下で違いがある。 |
| 隔年結果 (かくねんけっか) |
・果実のできが1 年おきに良・不良を繰り返すこと。 ・果樹では、一般に放任してある年に着花・結果が多くなると、その翌年は着花・結果ともに少なくなり翌々年にはまた多くなるという現象を生じる、過剰な結果が樹勢を弱めるからで、適度な剪定などによって防ぐことができる。 |
| 株間(かぶま) | ・隣の株との間の植え付け距離、条間距離とは違うので注意!! 例)株間30 〜40cm |
| カリ肥料 (かりひりょう) |
・肥料3 要素中の1 つであるカリウムを主体にした肥料。 ・『草木灰』、『硫酸加里』、『塩化加里』など。 |
| 過燐酸石灰(かりんさんせっかい) | ・リン鉱石を粉砕し、これに硫酸を加え混合して反応させたリン酸肥料。 |
| 緩行性肥料(かんこうせいひりょう) | ・分解吸収が徐々に行なわれ、肥効がゆるやかに現れる肥料。 ・即効性肥料と遅効性肥料の中間のもの。 |
| 気孔(きこう) | ・植物の体表にあって、ガス交換や蒸散のために空気や水が出入りする器官。 ・一般に葉の裏側に多く、外界の条件によって開閉する。 |
| 苦土(くど) | ・通称マグネシウム、葉緑素の形成に不可欠な物質で、マグネシウムが欠乏すると葉が黄化する。 ・肥料では、酸化マグネシウム(MgO)の形で、酸性土壌の改良も兼ねて施される。 |
| 光合成 (こうごうせい) |
・緑色作物が、光エネルギーを用いて炭酸ガスを固定(有機物に転化)する過程。 ・そのとき水が消費され、固定され炭酸ガスとほぼ同量の酸素を発生する。 |
| 好光性種子(こうこうせいしゅし) ⇔嫌光性種子 |
・光があたるとよく発芽するが、暗黒中では全然発芽しないか発芽の悪い種子。 例)タバコ、シソ、ゴボウなど |
| 催芽(さいが) | ・種子や球根などを、播種または植え付け前に少し発芽させること。 ・発芽しにくいものでは、催芽により発芽を一様にし、生育を早める効果がある。 |
| 酸性肥料(さんせいひりょう) | ・肥料自体の水溶液の性質が酸性を示す化学的酸性肥料と、主成分が吸収された後の残留成分が土壌反応を酸性にする生理的酸性肥料がある。前者は過燐酸石灰など、後者は硫酸アンモニア・硫酸カリなど。 |
| 酸性土壌(さんせいどじょう) | ・一般に降雨や酸性肥料の施用によって、置換性カルシウム・マグネシウムなどの塩基が流亡し、これらのイオンに換って水素イオンやアルミニウムイオンが土壌コロイドに吸着されるため、酸性化するとされている。 |
| 直播き(じかまき) | ・苗床で育苗することなしに、本圃(ほんぽ)に直接種子を播きつけること。 |
| 支柱根(しちゅうこん) | ・地上の節から出て、地中に入る太い根。 ・茎の支えとなり、上部より出た根は地面に到達せず気根状になることが多いが、下部からでたものは地中に入り、養水分の吸収も行なう。トウモロコシなどに見られる。 |
| 硝化細菌(しょうかさいきん) | ・硝化菌、硝酸化成菌。アンモニアを酸化して亜硝酸にする『亜硝酸菌』と亜硝酸を硝酸に酸化する硝酸菌がある。 ・いずれも土壌細菌で、肥料の分解・吸収に重要な働きをしている。 |
| 蒸散(じょうさん) | ・高等植物において、体内の水が水蒸気として体外に排出されることをいう。特に葉から空中に排出される。 |
| 硝酸態窒素(しょうさんたいちっそ) | ・土壌、肥料の中にある窒素の形態の一つ、水に溶けやすく肥効は速やかであるが、土壌に吸収保持されないから、雨水や灌漑(かんがい)水によって流失されやすい。 |
| 除草剤(じょそうざい) | ・『接触性除草剤』(薬剤が触れた部分だけを枯らす)と『移行性除草剤』(根や茎葉から吸収され他の場所へ移行して植物全体を枯らす)とがある。 ・また、『非選択性除草剤』(すべての植物を枯らす)と『選択性除草剤』(一部の植物だけを枯らす)がある。 |
| 芯止まり(しんどまり) | ・芯が伸びずに止まった状態になること、トマトでは2葉または1葉ごとに花房が発生し、花房のしたのわき芽が伸びるのが通常であるが、このわき芽が伸びないと芯が止まった状態となる。 |
| 中耕(ちゅうこう) | ・生育中の作物の作条の間を耕す作業、雑草などを除くとともに、土の物理的性質を改善する効果がある。 |
| 土寄せ(つちよせ) | ・中耕の一種で、畦の間の土を作物の株際に寄せ付けること、倒伏を防いだり排水を良くする効果がある。 |
| 飛び節成り(とびふしなり) | ・キュウリの着果習性の一つの型、各節に着果しないで、着果する節が連続しない(飛ぶ)のでこのように呼ぶ。 |
| 中生(なかて) | ・成熟期、収穫期を早・中・晩に分けたとき、早生と晩生の間のもの。 |
| 必須元素(ひっすげんそ) | ・植物の栄養として不可欠の元素。 ・炭素、酸素、水素、窒素、リン、イオウ、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、マンガン、ホウ素、亜鉛銅、モリブデン、塩素の16 元素。 ・はじめの9 元素を多量元素、後の7 元素を微量元素という。 |
| 被覆肥料(ひふくひりょう) | ・粒状肥料の粒表面を被覆加工したもの、粒表面を物理的に被覆することにより、水溶成分が流出するのを制御し、緩効化、遅効化を図っている。 |
| 肥料三要素(ひりょうさんようそ) | ・作物に特に施さなければならない窒素、リン、カリウムをいう。これらの三つの要素は、天然の供給量では、作物の需要を満たすには不十分なので、人工的に施す必要があり、実際には窒素(N)、リン酸(P2O5)、カリ(K2O)の形で施される。 |
| 複合肥料(ふくごうひりょう) | ・一般には、化成肥料と配合肥料を統合した呼び名であるが、肥料取締法では窒素、リン酸、カリの2 成分以上含有することを保証するもの。 |
| 分球(ぶんきゅう) | ・タマネギ栽培で早まきした大苗を植えつけた場合、春になって鱗茎(りんけい)が分かれること。 |
| ホットキャップ(ほっときゃっぷ) | ・スイカの露地直播栽培などで、株ごとに保温用に用いるプラスチックフィルム製のキャップ(小さな覆い) |
| ボトニング(ぼとにんぐ) | ・カリフラワーの花蕾(からい)の異常発育の一つの形で、早期に花芽分化を起こし、小さな花蕾のままになること。 |
| 有機質肥料(ゆうきしつひりょう) | ・動物または植物を原料とした肥料で、有機物を含んでいるもの。 ・有機質肥料では、動物質肥料(魚肥・骨肥)と植物質肥料(油粕肥・緑肥など)に分けられる。 |
| リーフィーヘッド | ・カリフラワーで花芽分化した後、高温のための花蕾の中に小葉が混生したもの。 |
| 燐酸(りんさん) | ・窒素、カリと並ぶ肥料三要素の一つ、P2O5で表され、生物体内で核酸の成分となるなど重要な役目をもつ。 |
| 早生(わせ)⇔晩生 | ・生育期間、播種してから開花、成熟、結実するまでの期間の短いものをいう。 |
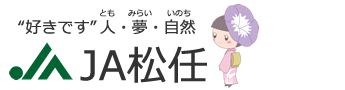


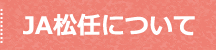




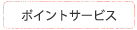
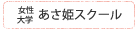


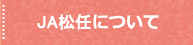
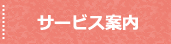
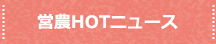
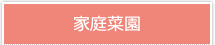
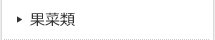
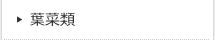
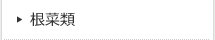

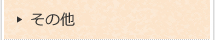
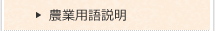

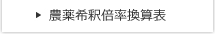
 果菜類
果菜類